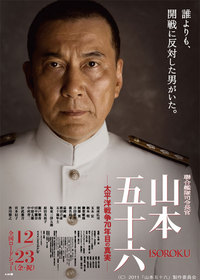2015年03月07日
「血と砂」(1965年・日本)
href="//img01.militaryblog.jp/usr/l/u/f/luftwaffe216patrouille/wyuiop.png" target="_blank">
1965年の東宝映画。往年の名優、三船敏郎が主役を務める「独立愚連隊」シリーズの最終作にあたる。
簡潔に言いたいが、素晴らしいよこりゃ。
監督の岡本喜八は日本戦争映画史に残る大作「日本の一番長い日」でメガホンを取った巨匠であるが、その2年前に本作を撮っている(このとき阿南陸軍大臣を演じた三船敏郎もまたすんばらしかった)。
独立愚連隊のようないわゆる娯楽戦争映画も撮った岡本監督であるが、「主張しない」ことの大切さがよく分かっておられる方である。
舞台は1945年8月の北支戦線。小杉曹長(三船敏郎)は銃殺刑になった下士官の扱いに対するいがみ合いから上官を殴り、その罪滅ぼしのために営倉入りと新兵を従えて八路軍の要衝であるヤキバ砦の攻略を命じられる。ただし新兵といっても彼らは軍楽隊で、鉄砲なんてまともに撃ったことがない。ついでに言えば筆下ろしもまだの小僧どもである。営倉入りメンツもけんかっ早い板前と、軍隊生活と言えば墓を作ったことだけという墓掘りのおっさんだけ。ついでに曹長を愛している慰安婦も連れて、決死のヤキバ攻略作戦は実行される…
いやあこの映画、なんてったってセリフ回しが最高だ。
「私の体は上品にできているからね…」
「大尉殿は、かわいそうであります」
「ほう、どうしてだ?」
「大尉殿の体が、上品だからであります!」バキィッ!!
「お春さんに抱いてもらう前に、全員最敬礼するように!」
「トランペット、おまえは○○だ。ホルン、チューバは○○…」
「海行かばでは淋しすぎます」
ユーモアたっぷりのセリフから、びりっとしびれる一言まで。
喋らせてスバラシイ。
そして八路軍(何百人いるんですか笑)との熾烈な戦闘。
たった十数名でヤキバを落とさなければならない必死の戦い。
戦わせてもスバラシイ。
とにかく見どころもりだくさんなのだ。
まずオープニングからぐっとひきこんでくる。
スタッフロールが流れ始めると、大写しになった軍楽隊の少年たちが、中国大陸の荒野でステップを踏みながら「聖者の行進」をこれでもかと吹き鳴らすのだ。
それもとびきりにジャジーで、「ヤーヤーヤー!」と掛け声も入る。
音楽を吹く嬉しさや楽しさが力いっぱい表れている。そこには黄土色やカーキ色に染め上げられた辛気臭さは無い。
この映画は「戦争つれえ…」「帰りてえ…」「やだあ…」みたいなのが無いのに、素晴らしい反戦映画として仕上がっている。
まあ当然のことだが、物事は隠さないと深みが出ないのである。最初からおっぴろげていたら薄っぺらいのである。
ここは巨匠岡本監督の真骨頂である。上のような女々しいことは一切言わないのに、戦争に対する虚しさや悲しさが強く伝わってくる。
最近の日本の戦争映画と言ったらみんなして本土の奥さんに「必ず帰ってきます」なんて手紙書いてもれなく死亡フラグを立てるのであるが、あれはそもそも死ぬと分かっているからこそ、心配を掛けないようにと書いてるんであって、マジで帰れると思ってるわけないと思うのは俺だけだろうか。
なんか本当は帰りたかったんだけど不幸にも死んじゃったみたいに描いてないか?
日本軍の戦死者は終戦までにおおよそ2百万人。4人に1人は生きては帰ってこられなかったんだぞ。
ただ各国の戦死者数はココを見てくれ。日本なんてまだ甘いくらいだろう・・・
作品の話に戻ろう。
主人公である小杉曹長は小憎い男で、何と言うんだろうか、石原裕次郎や若大将の兄貴みたいな感じと言うか、とにかく男らしい。
小杉曹長の不器用で下手くそな生き方が、昭和堅気な三船の演技とマッチして実に生き生きとしているのだ。
果敢な行動力、ふと見せる優しさ、勢い任せに喧嘩しちゃうところ、どこも不思議と愛らしいんだよなあ。
でもね、こんな調子で一人ひとり語ってたらキリが無いんですわ(笑)
軍楽隊も、板前も、墓掘りも、慰安婦もみんな素晴らしい。上官も他の兵隊も、八路軍ですら、この芝居の上手さには驚かされる。
この映画を観終わる頃には、どのキャラクターも一種かけがえのない存在くらいなっているのだ。もうこいつら一人ずつでも映画撮れちゃうって。
魅力を前部語るのは無理なので、かいつまんでいくけど。
軍楽隊の怖いけど必死で頑張る姿、
板前の気風の良い江戸っ子肌、
墓掘りの頼りないけど憎めないキャラ、
慰安婦の小杉を信じる続ける心。
みんな大好きい!!!(錯乱)
魅力的だからこそ、ラストに向かうにつれて涙腺が…
ごめん、以下ネタバレ入るけど許してください。
軍楽隊の少年たちも、ツイてないやつから戦死していく。
みんなそれを乗り越えてだんだん強くなっていき、ついにはヤキバも攻略。
あとは増援を待つだけなんだけど、その増援が来ることはない。佐久間隊は撤収を開始していた。小杉たちは置き去りにされたのだ。
やがて八路軍が大挙して反撃してくる(マジで何人いるんだよってくらい出てきます)。みんな果敢に応戦するんだけど、もう圧倒的な数の前にどうしようもない。みんなボロボロだ。それでもなんとか踏ん張って、見事夜明けまでヤキバを守り抜く。
だが一番頼り強く、また心の支えであった小杉が夜戦の傷がもとで戦死。みんな悲しみに暮れる中、八路軍は容赦なく反撃を開始する。
弾も無い。増援も無い。小杉もいない。
できることは音楽を奏でることだけになった。
そう、あの「聖者の行進」を。
砲弾降りしきり、銃弾の雨が打ちつける中、少年たちは最後の一人になるまで演奏を続ける。
何回も、何回も、
「ドミファソ ドミファソ ドミファソミドミレ ミミレド ドミソソファ ミファソミドレド」
家族の前でなかったら思い切り泣いてしまうところだった。
みんな音楽を奏でるのが大好きだった。生きている喜びを音楽で100%表現できていたのだ。
彼らが死ななければいけなかった理由なんてあるのだろうか。
そしてヤキバの襲撃、下士官の処刑が、思わぬ形で一本の糸でつながるとき、この戦いの虚しさは頂点に達する。
「その日、八月十五日」
いやあ、これは泣けますよ。
今からちょうど50年前の映画だけど、いまこんな映画、撮ることなんてできないんだろうな。
やっぱ忘れるってのは怖いことだね。忘れちゃったらさ、もう誰も再現なんてできないんだよ。
原爆や東京大空襲をまるで天災みたいに教科書に書いてるようじゃどうしようもない。
戦争がまだ生々しかった時代だったからこそ描けた作品なんだろう。
必見です。

1965年の東宝映画。往年の名優、三船敏郎が主役を務める「独立愚連隊」シリーズの最終作にあたる。
簡潔に言いたいが、素晴らしいよこりゃ。
監督の岡本喜八は日本戦争映画史に残る大作「日本の一番長い日」でメガホンを取った巨匠であるが、その2年前に本作を撮っている(このとき阿南陸軍大臣を演じた三船敏郎もまたすんばらしかった)。
独立愚連隊のようないわゆる娯楽戦争映画も撮った岡本監督であるが、「主張しない」ことの大切さがよく分かっておられる方である。
舞台は1945年8月の北支戦線。小杉曹長(三船敏郎)は銃殺刑になった下士官の扱いに対するいがみ合いから上官を殴り、その罪滅ぼしのために営倉入りと新兵を従えて八路軍の要衝であるヤキバ砦の攻略を命じられる。ただし新兵といっても彼らは軍楽隊で、鉄砲なんてまともに撃ったことがない。ついでに言えば筆下ろしもまだの小僧どもである。営倉入りメンツもけんかっ早い板前と、軍隊生活と言えば墓を作ったことだけという墓掘りのおっさんだけ。ついでに曹長を愛している慰安婦も連れて、決死のヤキバ攻略作戦は実行される…
いやあこの映画、なんてったってセリフ回しが最高だ。
「私の体は上品にできているからね…」
「大尉殿は、かわいそうであります」
「ほう、どうしてだ?」
「大尉殿の体が、上品だからであります!」バキィッ!!
「お春さんに抱いてもらう前に、全員最敬礼するように!」
「トランペット、おまえは○○だ。ホルン、チューバは○○…」
「海行かばでは淋しすぎます」
ユーモアたっぷりのセリフから、びりっとしびれる一言まで。
喋らせてスバラシイ。
そして八路軍(何百人いるんですか笑)との熾烈な戦闘。
たった十数名でヤキバを落とさなければならない必死の戦い。
戦わせてもスバラシイ。
とにかく見どころもりだくさんなのだ。
まずオープニングからぐっとひきこんでくる。
スタッフロールが流れ始めると、大写しになった軍楽隊の少年たちが、中国大陸の荒野でステップを踏みながら「聖者の行進」をこれでもかと吹き鳴らすのだ。
それもとびきりにジャジーで、「ヤーヤーヤー!」と掛け声も入る。
音楽を吹く嬉しさや楽しさが力いっぱい表れている。そこには黄土色やカーキ色に染め上げられた辛気臭さは無い。
この映画は「戦争つれえ…」「帰りてえ…」「やだあ…」みたいなのが無いのに、素晴らしい反戦映画として仕上がっている。
まあ当然のことだが、物事は隠さないと深みが出ないのである。最初からおっぴろげていたら薄っぺらいのである。
ここは巨匠岡本監督の真骨頂である。上のような女々しいことは一切言わないのに、戦争に対する虚しさや悲しさが強く伝わってくる。
最近の日本の戦争映画と言ったらみんなして本土の奥さんに「必ず帰ってきます」なんて手紙書いてもれなく死亡フラグを立てるのであるが、あれはそもそも死ぬと分かっているからこそ、心配を掛けないようにと書いてるんであって、マジで帰れると思ってるわけないと思うのは俺だけだろうか。
なんか本当は帰りたかったんだけど不幸にも死んじゃったみたいに描いてないか?
日本軍の戦死者は終戦までにおおよそ2百万人。4人に1人は生きては帰ってこられなかったんだぞ。
ただ各国の戦死者数はココを見てくれ。日本なんてまだ甘いくらいだろう・・・
作品の話に戻ろう。
主人公である小杉曹長は小憎い男で、何と言うんだろうか、石原裕次郎や若大将の兄貴みたいな感じと言うか、とにかく男らしい。
小杉曹長の不器用で下手くそな生き方が、昭和堅気な三船の演技とマッチして実に生き生きとしているのだ。
果敢な行動力、ふと見せる優しさ、勢い任せに喧嘩しちゃうところ、どこも不思議と愛らしいんだよなあ。
でもね、こんな調子で一人ひとり語ってたらキリが無いんですわ(笑)
軍楽隊も、板前も、墓掘りも、慰安婦もみんな素晴らしい。上官も他の兵隊も、八路軍ですら、この芝居の上手さには驚かされる。
この映画を観終わる頃には、どのキャラクターも一種かけがえのない存在くらいなっているのだ。もうこいつら一人ずつでも映画撮れちゃうって。
魅力を前部語るのは無理なので、かいつまんでいくけど。
軍楽隊の怖いけど必死で頑張る姿、
板前の気風の良い江戸っ子肌、
墓掘りの頼りないけど憎めないキャラ、
慰安婦の小杉を信じる続ける心。
みんな大好きい!!!(錯乱)
魅力的だからこそ、ラストに向かうにつれて涙腺が…
ごめん、以下ネタバレ入るけど許してください。
軍楽隊の少年たちも、ツイてないやつから戦死していく。
みんなそれを乗り越えてだんだん強くなっていき、ついにはヤキバも攻略。
あとは増援を待つだけなんだけど、その増援が来ることはない。佐久間隊は撤収を開始していた。小杉たちは置き去りにされたのだ。
やがて八路軍が大挙して反撃してくる(マジで何人いるんだよってくらい出てきます)。みんな果敢に応戦するんだけど、もう圧倒的な数の前にどうしようもない。みんなボロボロだ。それでもなんとか踏ん張って、見事夜明けまでヤキバを守り抜く。
だが一番頼り強く、また心の支えであった小杉が夜戦の傷がもとで戦死。みんな悲しみに暮れる中、八路軍は容赦なく反撃を開始する。
弾も無い。増援も無い。小杉もいない。
できることは音楽を奏でることだけになった。
そう、あの「聖者の行進」を。
砲弾降りしきり、銃弾の雨が打ちつける中、少年たちは最後の一人になるまで演奏を続ける。
何回も、何回も、
「ドミファソ ドミファソ ドミファソミドミレ ミミレド ドミソソファ ミファソミドレド」
家族の前でなかったら思い切り泣いてしまうところだった。
みんな音楽を奏でるのが大好きだった。生きている喜びを音楽で100%表現できていたのだ。
彼らが死ななければいけなかった理由なんてあるのだろうか。
そしてヤキバの襲撃、下士官の処刑が、思わぬ形で一本の糸でつながるとき、この戦いの虚しさは頂点に達する。
「その日、八月十五日」
いやあ、これは泣けますよ。
今からちょうど50年前の映画だけど、いまこんな映画、撮ることなんてできないんだろうな。
やっぱ忘れるってのは怖いことだね。忘れちゃったらさ、もう誰も再現なんてできないんだよ。
原爆や東京大空襲をまるで天災みたいに教科書に書いてるようじゃどうしようもない。
戦争がまだ生々しかった時代だったからこそ描けた作品なんだろう。
必見です。
Posted by NEU at 01:36│Comments(0)
│戦争映画・大日本帝國