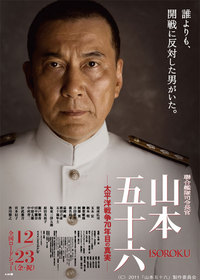2015年06月08日
おかあさんの木(ネタバレ注意)
はじめに断っておきますけどね、俺は右翼ですよたぶん。
「天皇陛下万歳」とか「中韓を皆殺しにしろ」とかまではいかないんで、にわか右翼ですかね。
まあそんな奴の意見なんで真に受けないでください(笑)
「おかあさんの木」
2015年の東映映画。
「天皇陛下万歳」とか「中韓を皆殺しにしろ」とかまではいかないんで、にわか右翼ですかね。
まあそんな奴の意見なんで真に受けないでください(笑)
「おかあさんの木」
2015年の東映映画。
この映画は「戦争映画を見て作った戦争映画」である。
決して戦時のお勉強などしていないと断言できる、ステレオタイプな道徳映画で、またそのせいで非常に思想臭い映画である。
この映画を観終わった観客の感想の100人中99人くらいは予想できる。
「戦争はいけないと思った」
「戦争について考えさせられた」
「平和は大切だと思った」
おおむねこの辺のはずだ。当然である。そう思うようにできている映画だからである。
映画の構成自体も稚拙だが、肝心はそこではないので後述する。
大まかな話の流れ
用地買収でその土地にある7本の木を切らなければいけなくなり、長野県の職員が土地の持ち主であるサユリ(奈良岡朋子)のもとに説明に出向く。さゆりおばあちゃんは「あの木を切ったらいかん」の一点張り。なんでも、戦時中に息子を戦地へ送り出したミツ(鈴木京香)という女性が、不在の息子の代わりにと植えたものらしい。サユリは戦前から戦時にかけての激動の昭和を、ミツと7人の息子がどう生きていったかを語り出す・・・
という感じで始まるのだが、その後の展開は見なくても大体わかると思う。
この映画は作り手が何を考えているかが筒抜けだ。
「あの時代は辛かったんでしょ?言いたいことも言えなかったんでしょ?泣きたくても泣けなかったんでしょ?国民は辛い思いをして耐えていたんだよね?」
いかにも現代人が現代人の物差しで当時を知っているかのように語っていて、スクリーン越しに見えるその物知り顔には反吐がでる。
正直言ってこんな昭和はパラレルワールドだ。
他者からはみ出すのをなによりも嫌う日本人が、兵隊に出すのはいやだと役人に言ったりとか、おいおいと公衆の面前で泣いたりしがみついたりとか、そんなことは決してやらなかったと思う。あったとしても本当に例外だろう。
それが例外として成立するには、このミツさんのような状態に至るまでの前置きのドラマが必要だが、それが薄いためにただ辛いからわんわん泣いているようにしか見えないのは非常に残念だ。7人兄弟なんてこの時代珍しいわけでもなし、それだけではその後の展開への伏線としては盛り上げに欠けている。
戦地の子供たちが「生きよう」「生きて帰ろう」なんて口を開くたびに言うのも大きなマイナスだ。
食べるものもなく、敵の代わりにマラリアを持つ蚊と戦い、木の根を剥いで食べ、最後には死んだ仲間の肉を口にしていたような南方戦線で、そんなことを一言でもつぶやいたら、おそらく正気ではいられなくなると思う。
だから我慢したんだ。みんな我慢したのだ。我慢したから心が壊れていったのであって、そこが大きな勘違いである。
「野火」見ればわかるだろ。「生きて帰りたい」なんてまだ考えられるような生ぬるい状況だったらもうあと2、3年は戦争続いてました。
また、子供たちの
「日本は勝つに決まってる」
「神州不滅だよ」
なんてセリフが、信じて言っていないのが丸見えである。実際は信じていたはずだ。でなければ戦争にはいけない。だが露骨すぎるせりふ回し(あるいは演出)のせいで明らかに信じていないのだ。それは「行きたくないけど我慢していった息子たち」を作り上げるための演出であって、フィクションなのだ。
お母さんの木を植える行為が、はじめから墓作りにしか見えないのも悲劇の暗示としてあまりに露骨すぎる。原作の絵本がどうかは知らないが、映画がかなり誇張しているのは確かだ。リアリズムのかけらもない。
登場人物もすべてがステレオタイプ。
悪者の憲兵、堅物だと思っていたら最後は人間らしい心を見せる役人、国を信じている婦人たち、優しさを見せる上官、ずっと気になっていたかわいい幼なじみ、中国で出会った名も知らない少女。。。
こんな連中はもうゴマンと戦争映画にでてきたのだ。いくらなんでもひねりがなさすぎる。
一番最低だった役がある。役名は「反戦家」。
県庁に反戦の落書きをしたりビラをまいたりする男である。
劇中では彼の存在に関してなんの説明もないが、おそらくヨーロッパのパルチザンやレジスタンスほどではない、穏和な平和主義者として描きたかったのだろう。
冗談ではない。この時代にこんな行動をするのは十中八九「共産主義者」だ。だから警察が追っているのだ。当時は特別高等警察といって、共産主義を取り締まる専門の警察官までいたほどだ。共産主義はソ連から発信されたが、共産主義を嫌っていたのは日本もドイツもアメリカもイギリスもみんな同じである。共産主義は当時の日本にとって脅威だったのだ。
そして歴史を少しでもかじった方はわかると思うが、共産主義は権力独裁、相互不信、密告社会を形成し、戦中戦後にソ連と中国を中心に何千万人もの人間が命を落とすことになるのである。
この映画は安保闘争から大学闘争時代に流行した共産主義への夢をいまだに見ている。これはあまりにも危険すぎる。行きすぎた共産主義がなにを生むかはもう歴史が証明したはずだ。だがこの点も最後のほうで後述したい。
そして何よりもこの映画に決定的に足りないのは、戦争への反省である。
驚いたことにこの手の映画がすべからく謳っているはずの文句が、この映画の中にはまるで現れない。
ただただ戦争で苦しんだ市民を被害者意識丸だしで描いているにすぎない。
日本は加害者である。誰かに騙されたにしろ、勘違いしたにしろ、選択を誤ったにしろ、日本が外地に出動し他国を侵略したのは明白なる事実である。自衛だろうがなんだろうがその点は絶対に変わらないのだ。例えそうしなければ日本が滅んだとしても、侵略は侵略なのである。
ではなぜ侵略するような国になったか。誰がそれを支持したのか。
国民である。
日清、日露の戦勝に浮かれたのも国民。賠償金が少なかったと暴動を起こしたのも国民。軍隊が政治に武力で物申すという国家の軍としてあるまじき行為だった226事件を「高潔な志を持った立派な青年たち」と褒めちぎったのも国民。結果として軍を増長させ、さらには戦争を煽るだけ煽ったマスコミも国民。そして戦争で苦しみ、自分たちが苦しんだのは国と軍が悪かったんだと責めるのも国民。
だというのに、この映画の登場人物は上から下までみんな被害者だ。
誰がこの社会を作り出したのか、まるで反省が足りていない。
日本は民主主義国家でありながら、国民が政治に対して責任を負おうとしないきわめて幼稚な国家である。
GHQからもらっただけの、自分たちでなにも努力しないで得た民主主義を「戦後の平和主義」という耳障りの良い言葉に変換して70年もオナニーに耽っていただけで、後に残ったのは自分に都合のいい自由と崩壊したモラル、相互不信の世の中だけだった。
戦争への真摯な反省と検証があまりにも足りなさすぎる。
誰かのせいでひどい目にあった、と一番簡単な答えに逃げ込んで、自分たちは何も責任がなかったんだと言い張る。
日本が王制国家ならまだわかるが、国民が国家を形成する民主主義でこの言い訳はあまりにも無責任であり、民主主義を拝む資格は無いと俺は考えてしまう。
映画自体の粗はもう箇条書きで済ませることにする。
このサユリおばあちゃんのお話を聞いている役人と地元民。
説明に来たはずがあっさりと聞きに入ります。理由はありません。そういう構成ですから。木を切る話はどこへ?
おばあちゃんが窓にしがみついて泣き崩れるのも嘘くさすぎてひどい演出。しかも役人と地元民、くずおれるおばあちゃんを介抱しません。え、認知症のおばあちゃんじゃないの?
役人「木を切る説明をするんですね」
地元民「ええ、でもできれば、こういうのはお国が…ね?」
役人「お国なんて、やめてください」
なんだこの会話。アナーキーぶってふざけてんのかよ。
例によって現代人過ぎるかわいい幼馴染。不思議なことに日本の着物であるモンペですら現代人が着るとコスプレになるんだわこれが。
「出征兵士を送る歌」は1939年の歌。1936年に甲種合格ですぐ次のカットで召集されていたが、3年経ったようには見えないからここも間違いとみていい。
どうでもいい粗ばっかりじゃなかった気がするのは俺だけじゃないだろう。
「戦争について考えさせられた」
嘘つかないでよ。考えた気になっているだけで、それはすでに誰かの思想に誘導されています。じゃなければ、ネットのレビューで評価の高かったものの内容がここまで似ることはないはずだ。
この映画は道徳の教材にはなっても、戦争の、ましてや平和のお勉強にはなりません。
総評として、もしこの映画が俺の指摘通り「戦争映画を見て作った戦争映画」だったとしたら、作り手は無罪放免ではないが多少の同情の余地がある。日本の戦争ドラマをすべからくなぞればこんな映画にもなるだろうと予想がつくからだ。ステレオタイプな登場人物、あきらかに「アカ」の反戦家、想像通りに進む悲劇の展開…それらすべてが、「どこかで見たことがある」シーンなのだ。
ただ「反戦家」のように居るだけで主義思想を発信してしまう登場人物をそのまま出してしまったことは、実に浅はかで軽率、無思慮な構成だったと言う他ない。
俺自身の反省もあります。
俺は戦争映画だと思ってこの映画を見に行っちゃたこと
これはあるかわいそうなおばあちゃんを主人公にしたフィクションのヒューマンドラマだ。
つくづく、日本のマスメディアはフィクションだらけである。
6月10日追記。
何日か経つと怒り任せにまあ散々なことを偉そうに書いているようなので、思い出したいいシーンを追記します。
この映画の導入部分。すがすがしいほどスピーディで無駄がない。余計な説明や長ったらしい尺もないので、すんなりと映画に入り込むことができた。
(後半につれてgdgdになったのは別の問題)
特に、お父さんとお母さんの馴れ初め。このシーンはよかったな。単純に淡い恋のシーンとしてよかった。その後の展開へのパンチ力としてはいささか不足(というより別ベクトルだった)していたものの、これにクスリと来た人は多かったはず。
以上!
あと、ラスト。
てかこのラストじゃなかったらほんとに怒るよ。
Posted by NEU at 22:04│Comments(2)
│戦争映画・大日本帝國
この記事へのコメント
この作品って、5人兄弟の4人が戦死したことを聞いた東条陸軍大臣の直々の命令により、義烈空挺隊が最後に生き残った一人を救出に行く作品ですよね?
義烈空挺隊の隊長が亀の子爆弾でM4シャーマンと差し違えるのが忘れられません。
こうゆうギャグを友人にかましたら、世の中にはネタにしちゃいかんものがあるぞと怒られました。
義烈空挺隊の隊長が亀の子爆弾でM4シャーマンと差し違えるのが忘れられません。
こうゆうギャグを友人にかましたら、世の中にはネタにしちゃいかんものがあるぞと怒られました。
Posted by とおりすがり at 2015年06月09日 00:17
コメントありがとうございます。
確かに兄弟の設定はプライベート・ライアンに似たものを感じますよね。
まあ実際に救出に行く余力があるのは、アメリカぐらいのものでしょうけど。
確かに兄弟の設定はプライベート・ライアンに似たものを感じますよね。
まあ実際に救出に行く余力があるのは、アメリカぐらいのものでしょうけど。
Posted by 216 at 2015年06月09日 00:33
at 2015年06月09日 00:33
 at 2015年06月09日 00:33
at 2015年06月09日 00:33